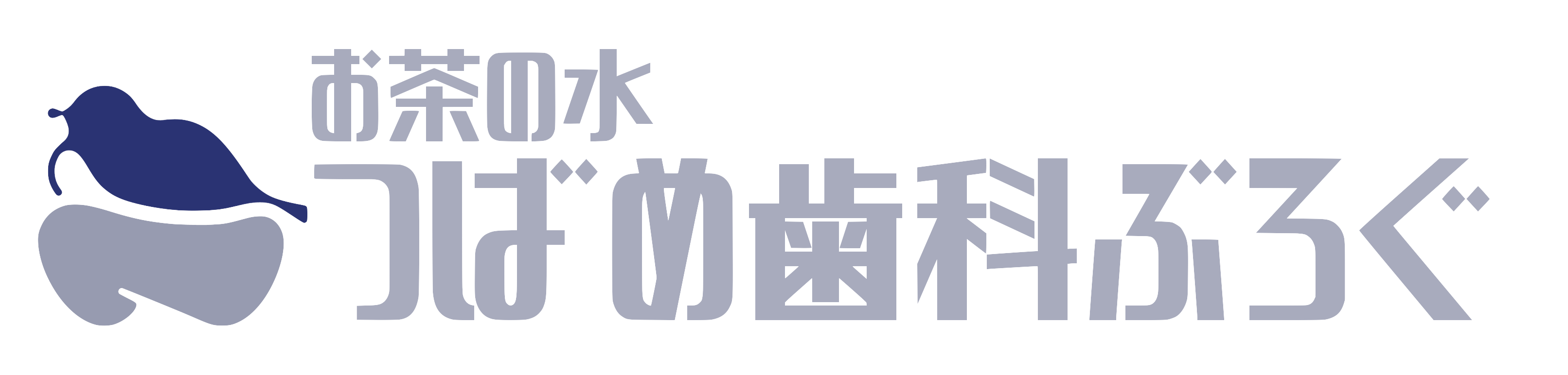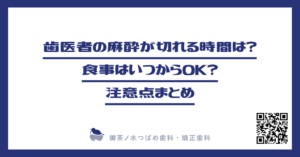歯医者さんでは麻酔を行った上での治療を行う事が多くあります。
痛みを感じることなく安心して治療を受けるために、歯科麻酔はとても大切な役割を果たしています。しかし、その効果が続いている間は、普段通りの感覚とは違うため、少し注意が必要です。
例えば、感覚がないためにうっかり頬の内側や舌を強く噛んでしまったり、熱い飲み物で気づかずに火傷をしてしまったり…といった思わぬトラブルにつながる可能性もゼロではありません。
この記事では、多くの方が気になる「歯医者の麻酔が切れるまでの一般的な時間」や、「麻酔が切れた後、いつから、どんな食事なら安全に始められるのか」、そして「麻酔が効いている間に特に気をつけるべきこと」について解説していきます。
治療後の疑問や不安を解消し、少しでも安心して快適に過ごせるように参考にして頂ければ幸いです。
1. 歯医者さんの麻酔、どれくらいで切れる?
歯医者さんで麻酔を使った後、あの独特の痺れた感覚がいつまで続くのか、気になりますよね。麻酔が切れるまでの時間は、治療の内容や使われた麻酔の種類、そして患者さんご自身の体質などによって変わってきますが、一般的な目安を知っておくと安心です。
麻酔の種類と持続時間の目安
歯科治療で使われる局所麻酔には、主に2つのタイプがあります。
- 浸潤麻酔(しんじゅんますい):
- 使われる場面: 比較的範囲の狭い治療(例:1本の歯の虫歯治療、歯茎の処置など)でよく使われます。
- 特徴: 治療する歯の周りの歯茎に注射し、その周辺だけをピンポイントで麻痺させます。
- 効果時間の目安: 一般的に、麻酔の効果(痺れや感覚の麻痺)が完全に切れるまでには1時間~3時間程度かかることが多いです。唇や頬の一部も一緒に痺れることがあります。
- 伝達麻酔(でんたつますい):
- 使われる場面: より広範囲に、または深く麻酔を効かせたい場合(例:下の奥歯の治療、親知らずの抜歯、インプラント手術など)に使われます。
- 特徴: 目的の場所を支配している、より太い神経の近くに麻酔薬を作用させ、広範囲の感覚を麻痺させます。下の奥歯の治療では、下顎の半分(歯、歯茎、舌、唇など)に痺れが出ることがあります。
- 効果時間の目安: 浸潤麻酔よりも長く効くのが特徴で、麻酔が完全に切れるまでには3時間~6時間程度、場合によってはそれ以上かかることもあります。
これらの時間は、あくまで一般的な目安です。次に説明するように、様々な要因によって麻酔の効いている時間は変わってきます。
麻酔の効き方に影響する要因
- 麻酔薬の種類と量: 歯科医師は、治療内容や時間に応じて、作用時間の異なる麻酔薬を選んだり、量を調整したりしています。
- 患者さんの体質: 麻酔薬の分解・代謝のスピードは人それぞれです。代謝が早い方は麻酔が切れやすく、ゆっくりな方は長引く傾向があります。
- 治療した場所: 骨の密度や血行の状態によって、麻酔薬の浸透や吸収のされ方が異なります。例えば、下顎の骨は上顎よりもしっかりしているため、麻酔が効きにくく、切れにくいことがあります。
- 年齢や全身状態: 年齢やその日の体調によっても、麻酔の効き方や切れるまでの時間に影響が出ることがあります。
感覚が戻ってくるサイン
麻酔が切れるときは、急に感覚が戻るというよりは、徐々に痺れが弱まっていくように感じられます。「ジンジン」「ピリピリ」といった感覚が出てくることもあります。
このように、麻酔が切れるまでの時間には個人差が大きいということを覚えておきましょう。もし、目安の時間を大幅に過ぎても痺れが全く取れないなど、心配なことがあれば、遠慮なく治療を受けた歯科医院に相談してください。
2. 麻酔が効いている間の食事はいつから?何を食べるべき?
治療が終わってホッとしたのも束の間、「お腹すいたな…」「いつになったらご飯を食べていいんだろう?」と疑問に思う方も多いでしょう。麻酔が効いている間の食事には、いくつか注意したい点があります。
食事を開始するタイミング:基本は「麻酔が切れてから」
最も大切な原則は「麻酔(痺れや感覚の麻痺)が完全に切れてから食事をする」ということです。
なぜなら、麻酔が効いている間は、唇や頬、舌などの感覚が鈍くなっているため、以下のようなリスクがあるからです。
- 口の中を噛んでしまう: 感覚がないため、気づかずに唇や頬の内側、舌を強く噛んでしまい、大きな口内炎や傷を作ってしまうことがあります。
- 火傷をしてしまう: 温度を感じにくくなっているため、熱い食べ物や飲み物で口の中を火傷してしまう危険性があります。
これらのトラブルを防ぐためにも、お口の感覚が普段通りに戻るまで、食事は控えるのが最も安全です。麻酔が切れる時間の目安は前の項目で説明した通りですが、ご自身の感覚で「痺れがなくなったな」と感じてから食事を再開するようにしましょう。
麻酔が効いている間に飲食したい場合
どうしても空腹が我慢できない、薬を飲むために何か口にしたい、という場合もあるかもしれません。もし麻酔が効いている間に飲食をする場合は、以下の点に注意を払ってください。
- 食べ物・飲み物の種類:
- 飲み物: 熱いものは絶対に避け、常温か冷たいものを選びましょう。
- 食べ物: 噛む必要のない、流動食や非常に柔らかいもの(例:ゼリー、ヨーグルト、プリン、冷めたスープ、おかゆなど)に限定しましょう。固形物は誤って噛んでしまうリスクが高いので避けてください。
- 食べ方・飲み方:
- 可能であれば、麻酔が効いていない側(感覚がある側)で、ゆっくりと慎重に飲食しましょう。
- ストローを使うと、意図せず喉の奥に流れ込んだり、吸う力で傷口(抜歯した場合など)に影響が出たりすることがあるので、状況に応じて注意が必要です。
- 温度確認: 食べ物・飲み物の温度は、唇などで確かめるのではなく、手で触れるなど他の方法で確認し、決して熱くないことを確かめてから口にしましょう。
麻酔が切れた後の最初の食事
無事に麻酔が切れ、感覚が戻ったら食事をしても大丈夫です。ただし、治療した箇所がまだ敏感になっている可能性もありますので、最初の食事は以下のようなものを選ぶと良いでしょう。
- 柔らかく、消化の良いもの: おかゆ、うどん、豆腐、卵料理、よく煮込んだ野菜、スープなど。
- 刺激の少ないもの: 硬すぎるもの、熱すぎるもの、冷たすぎるもの、辛いものなど、刺激物は避けた方が無難です。
特に抜歯などの外科的な処置をした場合は、治癒を妨げないよう、歯科医師から食事内容について具体的な指示がある場合があります。その際は、必ず指示に従ってください。
焦らず、お口の状態を確認しながら、ゆっくりと普段の食事に戻していきましょう。
はい、承知いたしました。「要注意!麻酔が効いている間に気をつけること」の項目について記述します。
3. 麻酔が効いている間に気をつけること
歯科治療で麻酔を使うと、痛みを感じずに処置を受けられますが、治療が終わって麻酔が効いている間は、普段と感覚が違うため、いくつか注意が必要です。思わぬ怪我やトラブルを防ぐために、以下の点に気をつけましょう。
① 口の中を噛まないように!麻酔が効いていると、唇や頬の内側、舌などを誤って噛んでしまっても痛みを感じません。気づかないうちに強く噛んでしまい、麻酔が切れた後に大きな口内炎になったり、出血したりすることがあります。食事はもちろん、無意識に口を動かしている時も注意が必要です。
② 熱い飲食物には要注意!食事の項目でも触れましたが、温度の感覚も鈍くなっています。普段なら「熱い!」と感じる温度でも気づかず、飲み物や食べ物で唇や口の中を火傷してしまう危険があります。麻酔が効いている間は、熱いものを口にするのは避けましょう。
③ 話しにくさ・飲み込みにくさも唇や舌が痺れているため、ろれつが回りにくくなったり、滑舌が悪くなったりすることがあります。また、飲み物や食べ物がうまく飲み込めない感覚になることも。無理に話したり、急いで飲み込んだりしないようにしましょう。これも麻酔が切れれば元に戻ります。
④ 口元からのよだれ唇周りの感覚が麻痺していると、口をしっかり閉じているつもりでも、無意識によだれが垂れてしまうことがあります。気になる場合は、ティッシュやハンカチを準備しておくと良いでしょう。
⑤ 指や舌で患部を触らない治療した場所や痺れている場所が気になって、指や舌で触りたくなるかもしれませんが、控えましょう。不必要に刺激を与えることで、痛みが出たり、治りが遅くなったりする可能性があります。特に抜歯などをした場合は、感染の原因にもなりかねません。
⑥ 激しい運動や長時間の入浴は控える麻酔そのものの影響というよりは、治療内容(特に抜歯などの外科処置)によりますが、血行が良くなると痛みが出たり、腫れがひどくなったりすることがあります。治療当日は、激しい運動や飲酒、長時間の入浴は避けて、安静に過ごすのがおすすめです。(歯科医師から特に指示があればそれに従ってください。)
【特に注意】お子様の場合小さなお子様の場合、痺れている感覚が不思議で、わざと唇や頬を噛んで遊んでしまうことがあります。大人が注意していても、一瞬の隙に強く噛んで、ひどい傷を作ってしまうケースが少なくありません。麻酔が完全に切れるまで、保護者の方がしっかりと様子を見て、「噛んじゃダメだよ」「触らないでね」と繰り返し声をかけてあげることが非常に重要です。
これらの点に注意して、麻酔が自然に切れるのを待ちましょう。もし、誤って口の中を強く噛んでしまった、火傷をしたかもしれない、など心配なことが起きた場合は、我慢せずに歯科医院に連絡してください。
4. まとめ
今回は、歯医者さんでの治療後に気になる「麻酔」について、効果が続く時間や食事のタイミング、注意点などを解説してきました。最後に、大切なポイントをもう一度確認しましょう。
- 麻酔が切れる時間は、種類や個人差が大きい
- 一般的な目安は、浸潤麻酔で1~3時間、伝達麻酔で3~6時間程度ですが、あくまで目安です。体質や治療内容によって異なります。
- 食事は、麻酔(しびれ)が完全に切れてからが安全
- 感覚がない状態で食事をすると、口の中を噛んでしまったり、火傷をしたりするリスクがあります。感覚が戻るまで待ちましょう。
- 麻酔が効いている間は、いくつかの注意が必要
- 無意識に口の中を噛まないように気をつける。
- 熱い飲み物・食べ物による火傷に注意する。
- 特にお子様の場合は、唇などを噛まないように保護者の方が見守ることが非常に重要です。
- 困ったこと・不安なことがあれば、遠慮なく歯科医院へ
- 麻酔が予想以上に長く続く、痛みがひどい、誤って口の中を傷つけてしまったなど、何か心配なことがあれば、自己判断せずに必ず治療を受けた歯科医院に連絡し、相談するようにしてください。
歯科治療後の麻酔が効いている時間は、少し不便に感じるかもしれませんが、安全に治療を行うためには欠かせないものです。正しい知識を持って、注意事項を守ることで、治療後のトラブルを防ぎ、安心して過ごすことができます。
この記事の情報が、皆さんの治療後の不安を少しでも和らげ、快適に過ごすための一助となれば幸いです。
治療のご予約は下記リンクよりいつでもお取り出来ます。キャンセルや2回目以降の治療予約に関しても行えます。
—————————————————————
御茶ノ水つばめ歯科・矯正歯科
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3丁目8-10メアリヒト御茶ノ水ビル1階
TEL:03-6281-7737
・JR御茶ノ水駅 お茶の水橋口改札 徒歩5分
・千代田線 新御茶ノ水駅B3b 徒歩5分
・神保町駅(半蔵門線、都営新宿線、都営三田線)A5 徒歩5分
・都営新宿線 小川町駅、丸の内線 淡路町駅B5 徒歩6分
・東西線 竹橋駅 3a 徒歩10分
—————————————————————